政策金利や短期プライムレートが上昇すると、住宅ローン金利も上昇することがあります。
では、実際にどれくらい負担が増えるのか、シミュレーションしてみました。
金利が上昇すると住宅ローンの返済金額は変わる?
| 変動金利 | 固定金利 | |
| 元利均等返済 | 変わる ※5年ルールで変わらないこともある | 変わらない |
| 元金均等返済 | 変わる | 変わらない |
金利見直しのタイミング
変動金利を選択している場合は(プランによりますが)年に2回、基準金利の見直しがあります。
※住宅ローンの適用金利(実際に負担する金利)は、以下の式で計算されます。
適用金利 = 基準金利 - 優遇金利(条件に応じた優遇)
5年ルール、125%ルールとは?
多くの金融機関では、変動金利かつ元利均等返済の場合、「5年ルール」「125%ルール」という2つのルールによって返済金額が変わらないことがあります。
5年ルール
借入後、あるいは金利見直し後の5年間に金利が上昇したとしても、返済金額が変わらないというルールです。
ただし、月の返済金額に占める元金と金利の割合は変わります。
金利が上昇した場合は、月の返済金額に占める金利の割合が増加します。そのため、元金の減少が緩やかになり、最終的な支払総額は増えるということに注意が必要です。
125%ルール
金利の見直しによって月の返済額が上がったとしても、+25%に収めるというルールです。
月の返済は金利が優先されますが、25%の増額に収まらなかった場合は、未払利息として次回以降の支払いに繰り延べになります。
段階的に金利が1.5%上がると?
では、シミュレーションとして5年に1回金利が0.25%上昇、最終的に30年で1.5%金利が上昇したときの支払金額を見てみます。
借入条件は、以下のとおりとします。
- 借入金額:4,000万円
- 返済期間:35年(420回払)
- 適用金利:1.0%(初回時)
- 返済方法:元利均等返済
- 変動金利(年2回変動)
金利変動による月の返済金額の変更は、以下のようになります。
| 支払い回数(回目) | 月の返済金額(円) | 適用金利(%) |
|---|---|---|
| 1 | 112,914 | 1.0 |
| 61 | 116,990 | 1.25 |
| 121 | 120,497 | 1.5 |
| 181 | 123,390 | 1.75 |
| 241 | 125,625 | 2.0 |
| 301 | 127,160 | 2.25 |
| 361 | 127,954 | 2.5 |
もしこのように支払金額が変わったとしたら、最初から最後まで金利が変わらなかったときと、金利が徐々に上がっていったときの支払総額には、差が生まれます。
| 支払総額(円) | |
|---|---|
| 全期間で変動なし | 47,423,880 |
| 徐々に金利が上昇 | 51,271,800 |
支払総額では、約384万円の差となりました。
ちなみに、同じ金額を固定金利2.5%、元金均等返済で借り入れたときの支払総額は、57,541,667円となります。
シミュレーション以上に短期間で、あるいは急角度で金利が上昇する場合、金利負担はシミュレーション以上に高まります。
金利は残債に対して生じるため、返済回数が少ないときに金利が大きく上昇したほうが金利分の負担は重くなります。
シミュレーションでは、5年に1回しか金利が上昇していないため、5年ルールや125%ルールの影響を受けていません。
短期間で金利が急上昇した場合、金利分の支払いが増え、最終的な返済金額がさらに膨れる可能性もあります。

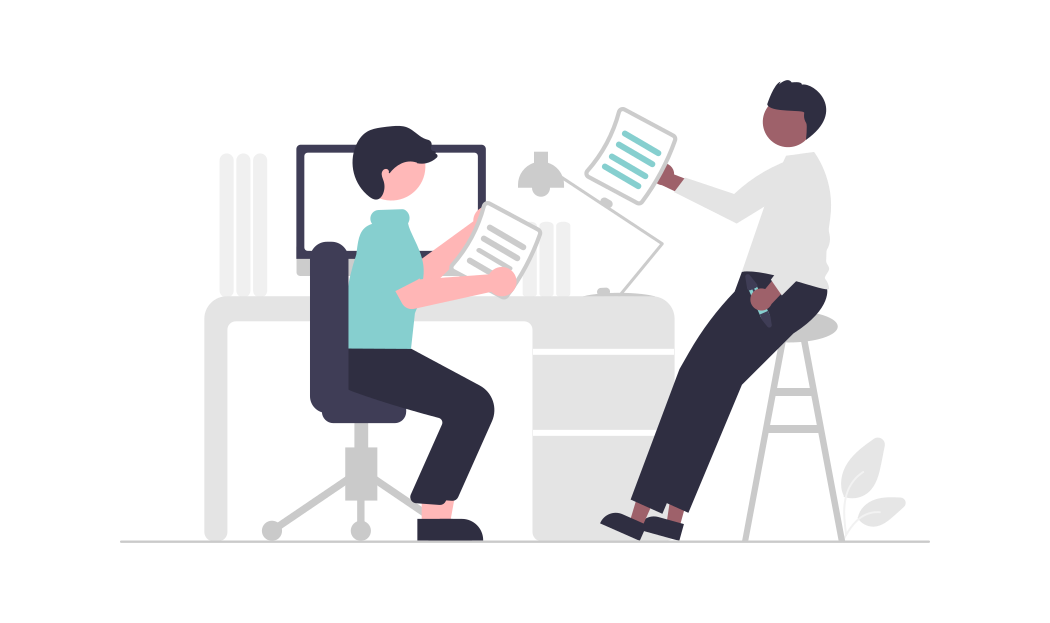
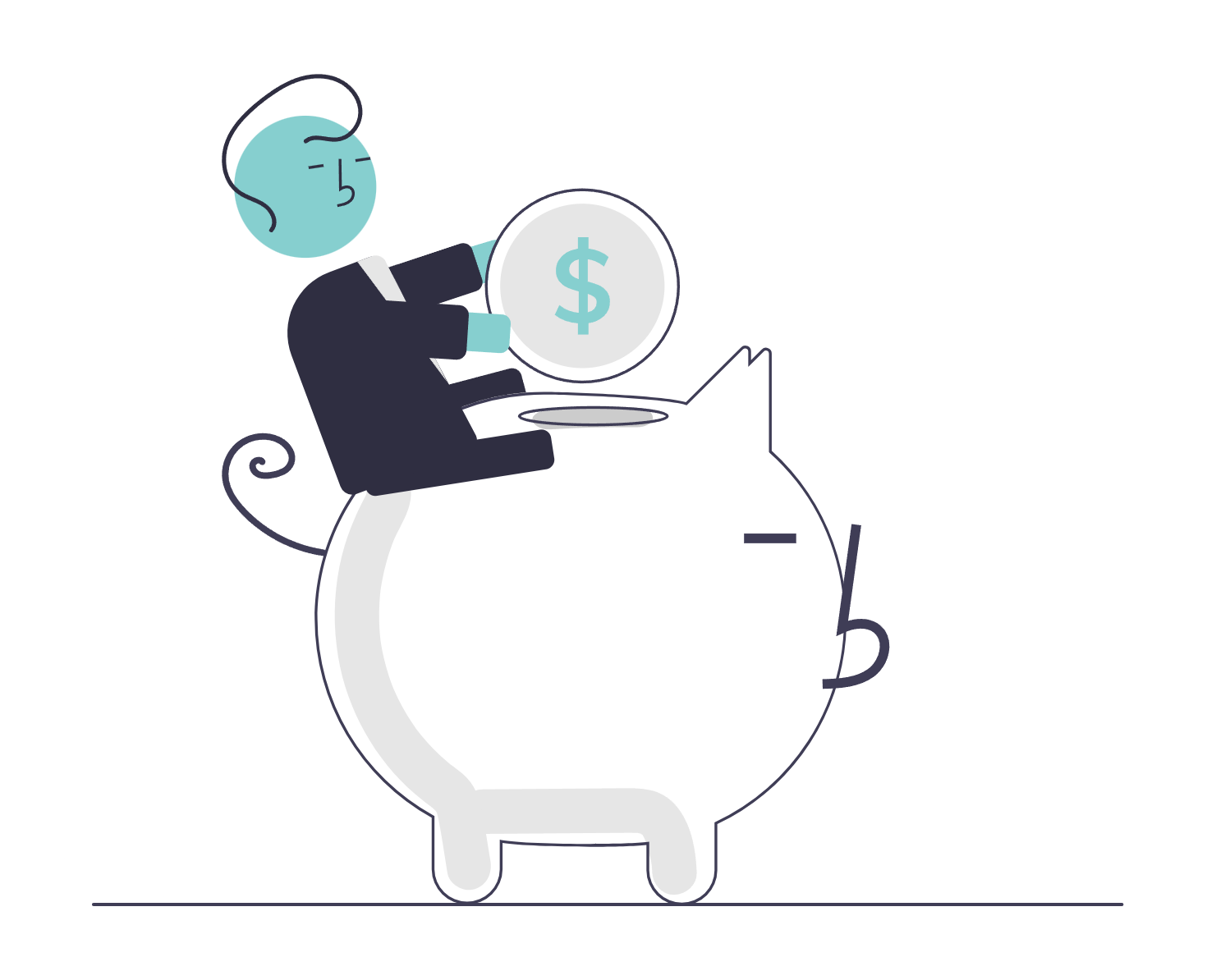
コメント