ふるさと納税は一見してわかりにくいところがありますが、本記事ではできるだけわかりやすく解説していきます。
※この記事では、正確性よりわかりやすさを優先して説明していきます。イメージとしてご理解ください。
ふるさと納税とは
自分が住んでいる地域以外に税金を払うと、そのお礼として返礼品を受け取れる制度です。
返礼品には、食品・酒・家具・家電・サービス利用券などさまざまなものがあります。返礼品に共通しているのは、その地域の特産品であるということです。
税処理の面から見ると、ふるさと納税は寄付金として扱われます。寄付金を支払うと税金を前払いした扱いになるため、支払済みの所得税が還付(返金)されたり、翌年度の住民税が減額されたりします。
あくまで前払いのような扱いなので、最終的に支払う金額は同じです。それでも返礼品が受け取れるため、その分お得とされています。
ワンストップ特例制度を使うときのイメージ
ワンストップ特例制度を使うと、自治体ごとに書類1枚を郵送することで税処理を行ってくれます。
例えば、来年度に120,000円の住民税を支払う人がいたとします。
今年に20,000円のふるさと納税をすると、ふるさと納税から自己負担額(2,000円~)を引いた金額18,000円が控除されます。
つまり、来年度に支払う住民税は102,000円となります。
ふるさと納税金額と来年度の住民税を合わせると、総支払額は122,000円になりますが、負担額が2,000円増えるだけで返礼品を受け取れることがわかります。
これがお得と言われる理由です。
今回は20,000円のふるさと納税でしたが、この金額には上限額があります。上限額は、支払う税金をもとに決まります。
寄付金控除の処理方法
より専門的な用語で説明すると、ふるさと納税した金額から自己負担額2,000円を引いた金額が寄付金控除となります。
寄付金控除額は住んでいる自治体ごとに上限が定められていて、上限を超えた分は自己負担額になります。
確定申告とワンストップ特例制度のどちらがお得か?という話題が上がるときがありますが、結論から言えばどちらでも変わりません。
確定申告する場合
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除、かつふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除があります。
言い換えると、今年にふるさと納税した場合、今年の所得税から控除された金額が還付(払いすぎた所得税が返金)され、来年の住民税が安くなります(来年分を今年に支払うイメージ)。
ワンストップ特例制度を利用する場合
確定申告が不要な人(年末調整がある人など)が、5団体以下の自治体にふるさと納税する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を使えます。
ワンストップ特例制度では、翌年の住民税からの控除はありますが、所得税からの控除はありません。
勘違いされがちですが、所得税からの控除がないから寄付金控除額が減るというわけではありません。全額が住民税から控除されるという扱いに変わるだけです(寄付金控除額の上限が定められているため、どちらを選択しても利用できる金額は変わらない)。

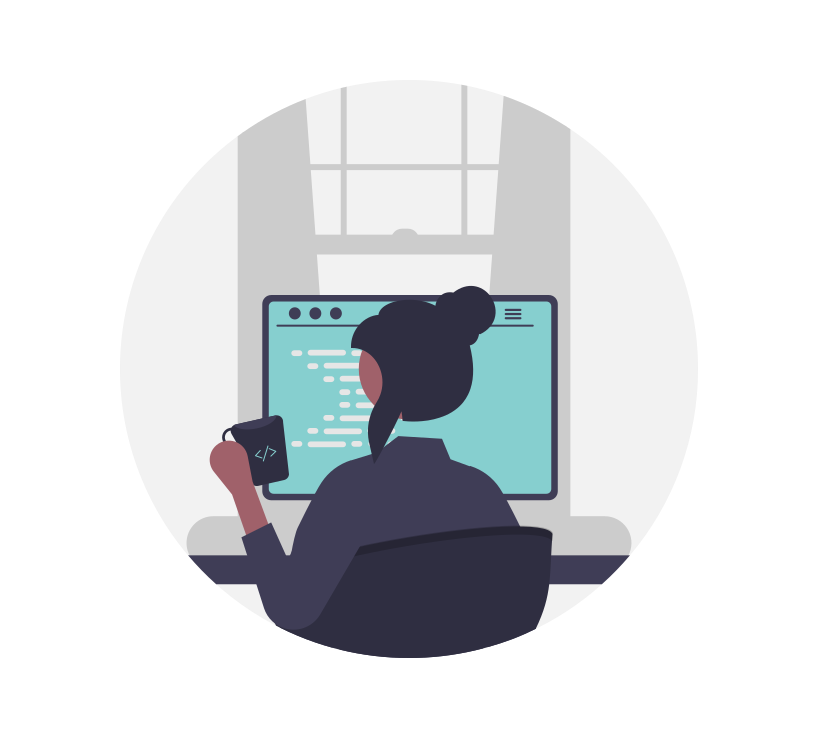

コメント